彼は誰に「話しかけている」のか―<見る―見られる>の関係性が作り出す共犯関係
Infoseek ニュース - ニュース速報、芸能スクープなど満載
最近ワイドショーや新聞を騒がせているこの事件だが、ここまで大きな扱いをされているのは、事件の猟奇性のほかに犯人が実に「マスメディア的」なタイプの人間であることに由来するのではないか。
一方で、星島はマスコミ取材にも積極的に応じた。事件に動揺して他の住民は口が重いのに、星島だけは冗舌だった。事件翌日の19日には報道陣に30分以上も対応し、警察の捜査状況や東城さん姉妹の印象だとかをペチャクチャと話していた。
彼が「ペチャクチャ」と話していた相手は、果たして誰だったのか。テレビカメラの向こうにいる、我々である。テレビの向こうで自分のことを見(てい)るであろう、「マス」である。我々はテレビに映る彼の姿を見ることで、彼と無言の「会話」をしている。彼の姿をテレビを通じて見ることは、彼が想定した「会話」の相手として、彼の用意したフレームの中にお行儀よく収まることを意味する。
また彼は「模範的」市民も華麗に演じている。
その上、マンション周辺で警戒に当たる警察官に「おはようございます」「ご苦労さまです」とマメに声を掛け、そうした姿も不審に思われていた。
これほどまでに「マスメディア」的な規律訓練の行き届いた人間はそういない。警察に進んで協力し、好意的な「模範的」市民であり、テレビを通して「大衆」と対話する。マスメディアを介した<見る―見られる>という関係性を余すところ無く内面化した人間である。
そしてこのマスメディア的な意味での「優等生」を作り出すのは、無論マスメディアを通じて「見ること」への欲望を持った我々である。彼は我々に話しかけ、我々は彼に話しかける。彼は我々に対して振る舞い、我々は彼に対して振る舞う。この共犯関係は、マスメディアが今のままである限り、逃れられない。
ではこれがインターネットだったら? すぐに思い出されるの「くまぇり」なる放火犯が、自らのブログでその犯行を客観的事実として記していた事件だろう。
江東の事件では、犯人と視聴者の間にある共犯関係のほかに、マスメディアそのものと犯人の間にも共犯関係があった。彼はマスメディアがこの画像を使うだろうと考えて喋り、またマスメディアもその先読みに応えた。この二重の共犯関係によって彼と我々との「対話」は成り立っていた。
放火事件の方では、マスメディアと犯人との共犯関係はない。それを介さずとも彼女はブログを使って我々と「対話」できた。ブログを使うことで、<見る―見られる>の関係性を自らプロデュースできた。だが犯人が見る人間の欲望を先読みし、見られる者としての振る舞いを自ら規定するという図式は、マスメディアを使おうがブログを使おうが変わらない。むしろ後者の方が敷居が下がったと言える。
テレビ、新聞、雑誌、ブログ、SNS、ミニブログ、動画サイト……見る者と見られる者の関係を作り出すメディアはこれらからも増え続ける。だがどのように形を変えようとも、我々は見ることの欲望と見られることの欲望が作り出す共犯関係からは逃れられない。インターネットの普及で様々なことが「変わった/変わる」といわれる中で、僕個人は「では何が変わらないのか」を見ていきたいと考えているのだが、これもまたそうした変わらぬことのうちの一つなのだろう。
デッドエンド・ジョブと若者―「ワープア論壇」の踏み絵
昨年度ゼミでお世話になった先生の文章がはてブでちょっと話題になった。
五十嵐泰正「「ババ抜きゲーム」は続くのか?――国内第三世界化と外国人労働者」
従来は家庭の中で女性に押し付けられていた再生産労働が、マーケットに委託され低賃金かつ他の職業にステップアップする「ラダー」の無いデッドエンド・ジョブとして存在している。そしてこのデッドエンド・ジョブを誰が引き受けるのか、誰が「ババ」を引くのかという問題が日本でも顕在化している。
外国人にババを引かせるやり方は、フランスの暴動を見れば上手いやり方ではない。外国人を徹底して「外部化」し、ババを押し付け続けるのは非常に困難であり、数十年という時間をかけて徐々に「内部」と同化していくのは目に見えている。
この文章では一つの、というか消去法で残るのは「高齢者」であるという。だが恐らくこの国で回っている「ババ」は彼らが引くには少し荷が重過ぎるカードだろう。行政的にも遠い道のりだ。
本文ではババの押し付けという不毛な議論を最終的には保留しているが、あくまでデッドエンド・ジョブを誰に押し付けるのか、現状誰が押して付けられているのかという話は、しなければならない気がする。
前回のエントリで組み立てた、<生活>と<ライフスタイル>という上下構造をもう一度持ち出すと、消費社会の進展はこの構造的な分化の徹底を促す。衣食住など生活の基礎部分については、「同じものをより安く」という消費者の要求に答えるべく、ますます画一化・効率化の進んだシステムによって支えられていくだろう。一方でそれ以外の文化的な生活については、より一層の差異化と複雑化が求められる。再生産労働によって担われている<生活>と、その上に成り立つ<ライフスタイル>は、消費社会の進展に伴ってそれぞれの機能を特化させ、ますます逆のベクトルへと伸張していく。
デッドエンド・ジョブはこの<生活>を支えるシステムの一歯車として、今後も必要であり続けるだろうしまたその数は増えるだろう。そして彼らの待遇改善という案は社会全体のパイを増やす必要があり、それが出来るかどうかは景気の動向というきわめて不確定な要素に拠らざるを得ない。
今のところこうしたデッドエンド・ジョブについているのは一部の外国人、一部の高齢者、そして一部の学歴の低い者である。

- 作者: 本田由紀
- 出版社/メーカー: 大月書店
- 発売日: 2007/05
- メディア: 単行本
- 購入: 5人 クリック: 181回
- この商品を含むブログ (40件) を見る
ここで学歴を出すとまた炎上しそうな感はあるが、前回も紹介した本田由紀編のこの本に載る新谷周平の論文によれば、「ジモト」にたまりラダーの無いジョブを転々としながら暮らす若者の多くは、学校で規律訓練に失敗した者である。学歴社会の崩壊が叫ばれて久しいが、あれはどうも学歴というリソースの価値が社会全体で相対化されただけの話であって、例えば東大卒の人間と高卒の人間が同じように扱われるといったフラットな世界になったというわけではない。全体が地盤沈下しただけであって、まさに「戦争でも起きない限り」、そのようなフラットな社会はそうそう来ないだろう。学歴というリソースの無い者は依然として、いや以前にも増してラダーの無い、デッドエンド・ジョブに就かざるを得ない状況に陥っている。
さらに悲惨なのは、新谷論文を見るとそうしたデッドエンド・ジョブについている若者が自分たちの生活形式を比較的肯定していることだ。彼らは規律訓練から外れた「自由」な生活を送ること、そしてそうした生活を送る仲間がいる状態を一つのカルチャーとして感じ取っており、彼らのアイデンティティの拠り所となっている。彼らの自分たちの生活に対するメンタリティと、実際の生活様式がサーキットしている。片方がもう片方をお互いに承認しあうのだ。現状に満足する循環構造が出来上がっており、そもそもデッドエンド・ジョブから抜け出す必要性を感じることが出来ない。
本来、社会の流動化は既得権益を掘り崩し、それまで社会階層的に下位にいた者も上位を狙えるようなチャンス=ラダーを生み出す。そういう意味で、社会の流動化が徹底されればそれはそれでデッドエンド・ジョブに就くような人々にとっても望ましい傾向であるとも言える。しかし実際にこの国に発生している流動化は、どうも同じ階層の中で行き来する流動性であって、ステップアップのためのラダーを架けるような流動性ではない気がする。
若者の話に限って言えば、解決の方策は二つある。ひとつは規律訓練の徹底。もう一つは規律訓練の有無に拠らない、流動化の徹底によるステップアップのためのラダーの確保である。しかしそもそもこの話の起点となった「誰にババを押し付けるのか?」という議論に戻れば、解決の必要性そのものが相対化される。彼らは仲間と過ごし彼らの文化を肯定することで自らのデッドエンドな境遇を肯定している。ならば彼らの幸せな世界をわざわざ外側から壊すこともあるまい。そのままでいてくれ、と。
社会学的なことを言えば、そうした状況は傍観して済むものではない。「彼らの持つ『文化』がその生活を規定し、またその生活が『文化』を規定している。そして彼らは社会から『疎外』されているのだ!」などと言えばあっという間にお手軽サヨクの出来上がりである。だがそもそも彼らがその状況を望んでいるとすれば? 少なくとも「疎外」などとは感じていないとすれば? そして黙っていれば彼らに「ババ」を押してつけることができるとすれば? 我々はその循環に彼らを留めておくという誘惑に勝つことが出来るのだろうか?
誰がババを引くのか、という問題をここでも一旦留保するなら、昨今盛り上がっている「ワーキングプア論壇」なるものは、今現在実際に苦しみの声を上げている者だけでなく、気づかぬうちにババを引きそしてそのことを不満に思わぬ人々の目に、外の世界を見せることも必要なのではないか。寝た子は起こさぬほうが社会にとっても彼らにとっても得じゃないか、という声を振り切り、自分たちの主義主張を貫くことが出来るのか。その「踏み絵」にこの問題はなる可能性がある。
「東京から考える」再考―都市を考えるためのマトリックス
昨年秋の「柏から考える」(柏初上陸―「柏から考える」の感想 - No Hedge!)について、先日のゼミでもう一度考える必要があったので色々整理してみた。*1これは柏がどうというレベルではなく、おそらく「東京から考える」

東京から考える―格差・郊外・ナショナリズム (NHKブックス)
- 作者: 東浩紀,北田暁大
- 出版社/メーカー: 日本放送出版協会
- 発売日: 2007/01
- メディア: 単行本
- 購入: 12人 クリック: 118回
- この商品を含むブログ (252件) を見る
で提示された東・北田による「国道16号線的な都市へのアンチに対するアンチ」という泥沼にはまりそうな(はまった)議論を整理するきっかけになるだろう。
都市と個人を考えるとき、そこには都市から個人を考える視点と個人から都市を考える視点の二つが存在する。これを前提に二つの対立軸を示し、それを掛け合わせた平面図を提示する。
視点1.都市における個人―環境が個人に与える影響
「東京から考える」の議論をベースにすると、個人が都市で暮らす際に感じる「気楽さ」は二種類ある。
国道16号線的な「気楽さ」:インフラ的な「機能の多様性」が担保された気楽さ。空間的にも経済的にもバリアフリーであり、ヤンキーから家族連れまで日常生活の根本的な部分を幅広く支えることが出来る。
西荻窪的な「気楽さ」:サブカルチャー的な「文化の多様性」が担保された気楽さ。衣食住といった生身の「生活」というよりも、個人の趣向に基づいたライフスタイルを支える。
西荻窪的な「気楽さ」は、東浩紀が「怒っていた」通り、家族連れや老人には通用しない。一方で16号線的な「気楽さ」もまた必ずしも西荻窪的な「気楽さ」を包含しない。バリアフリーでありながら、北田暁大のような一人暮らしに近い生活をしている人にとってはあまりに「ファミリー」的な空間であり、いづらさを感じる。どちらの「気楽さ」も都市に何らかの規範を生み出し、あるカテゴリの人間に疎外感を与えている。これらは単純な二項対立というより以下の様な上部・下部構造になっていると思われる。
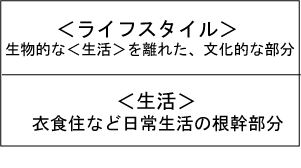
16号線的な「気楽さ」は<生活>において必要な資源を供給する「機能」が非常に優れていることを示している。誰でも衣食住は満たされる必要があり、あらゆる人間がいつでもそれらを満たされる機能的な側面が重要視される。16号線的な空間は<生活>空間であると言える。
一方で西荻窪的な「気楽さ」は、<ライフスタイル>における選択肢の多様性を示している。<生活>が満たされていることは前提にされている。西荻窪的な空間は<ライフスタイル>空間であるといえる。
「家族」としての日常生活は、<生活>が<ライフスタイル>を規定することが多い。一家四人を支える<生活>は選択肢が限定されており、それが同時に文化的な<ライフスタイル>も規定する。一方で一人暮らしのような人々は<ライフスタイル>によって<生活>を規定することも可能である。
視点2.個人のアイデンティティと都市―個人が都市に与える影響
個人の持つ都市に対する意識がどのように変わっているのか、またそうした意識とまちづくりがどのように関わっているのか。
(「東京から考える」)における「渋谷」:(特に東氏の)ヴァーチャルな地元意識を担保する。匿名的で、個人は都市に埋没する。ただしこうした記号的な「渋谷」意識は今は衰退している。
(例えば難波 功士『族の系譜学』における)「ウラハラ」:そのコミュニティに「所属」しているようなアイデンティティを担保している。顕名的で、個人同士のコミュニケーションによる「繋がり」が掛け金。都市は後景化し人々の繋がりが前景化する。
万人がイメージする記号に基づいた都市:スペクタル志向の空間。その記号の耐用年数が過ぎたときに凋落する。また記号にたよったまちづくりは単なる都市間競争に陥る可能性がある。
「繋がり」に基づいた都市:コミュニケーション志向の空間。実際の人間関係を掛け金にしたコミュニティを抱えるため、所属意識を促し、人々を都市に根付かせる可能性がある。ただし下北沢の例で分かるとおり、世代継承性やセキュリティのロジックで脆弱性を抱える場合が多い。
この10年20年で、ある都市の名前が万人に共通のイメージを喚起する時代は終焉を迎えたのかもしれない。代わりに台頭するのは大きな「都市」ではなく人々の「繋がり」を担保する小さな「コミュニティ」である。それは個人のメンタリティとしても、また都市が人々を取り込む際の戦略としてもそうしたものは有効であるらしい。(「渋谷」という記号が失効しても渋谷という都市そのものが勢いを失わなかったのは、その後コミュニケーション的な空間へと移行したからなのかもしれない)
ただこの「記号から繋がりへ」という現象は、あらゆる場所に通じる共時的な現象であるのか、それとも発展段階論的なモデルケースなのかは分からない。「渋谷」という記号が失効したのは、その記号が持つ実質的な機能が成熟しきってしまったからだとするならば、例えば「柏」等そのほかの中核都市ははそもそも記号として成熟しきっていない可能性がある。その場合、都市が取るべき戦略はおのずと変わってくる。
注意すべきなのは、記号的な都市にしても繋がりのあるコミュニティ的な都市にしても、<生活>の側面を犠牲にして<ライフスタイル>を重視しすぎるやり方では足下をすくわれるということだ。安定した<生活>空間を作らなければ、そこに容易に資本が流入し、せっかく作り上げた記号的な<ライフスタイル>空間も基盤から崩されることになる。またコミュニケーン志向の空間も、セキュリティや世代継承性といった<生活>空間への配慮を欠くとロジカルにカウンターされる。
<生活>―<ライフスタイル>:スペクタクル―コミュニケーション
以上のような、<生活>空間―<ライフスタイル>空間の軸と、スペクタクル志向空間―コミュニケーション志向空間という軸の二つを掛け合わせせると、一つのマトリックスが出来る。「東京から考える」やその他の文献で出てきた都市や地域を適当に当てはめてみた。それが以下の図である。
「『ジモト』意識で繋がる地方都市」というのは、友人関係を広げず地元の中学や小学校の友人だけで閉じてしまい、「ジモト」を大事にするという意識で繋がる関係性のことである。非正規雇用に就く若者が多い。詳しくは

- 作者: 本田由紀
- 出版社/メーカー: 大月書店
- 発売日: 2007/05
- メディア: 単行本
- 購入: 5人 クリック: 181回
- この商品を含むブログ (40件) を見る
における新谷周平の論文を参照。
秋葉原や原宿が矢印で移動させてあるのは、以前は<ライフスタイル>空間的でコミュニケーション志向だったのが、マスメディアへの露出を経ることで、大手の資本が多く参入し、スペクタクル志向の空間へと移行したのではないか、という推測に基づく。
またこれらは都市を外部から見たときのイメージを図式化したものなので、実際にそこに暮らす住人は異なる印象を持つだろう。もちろん、外部イメージを内側から取り込んでいる可能性もあるが。
この図式を作って言いたかったのは、どの都市なり地域なりがこの図のどこに当てはまるのか、ということより、「東京から考える」に見られるような、「国道16号線的な光景を嫌う三浦展vsそれのどこが悪いんだ的な東・北田」、「国道16号線的な光景万歳の東vsそれでも下北沢が好きな北田」、という単純な二項対立で話を展開させるべきでない、ということだ。都市が規定する個人の生活は二層構造になっており、この区別をまず前提にすれば、ジャスコ的なものと下北沢的な光景を比較するのが軸のずれた話だということが分かる。またそこにセキュリティガンガンの世田谷などの話を加えても、軸がやはりずれてしまう。話は単純な二項対立の中ではなく二項対立の掛け合わせによる平面の中で捉えたほうが分かりやすい。
ちなみにここにそれぞれの地域やコミュニティへのコミット具合とそれに伴う内部のコミュニケーションの変化という軸を加えると平面だけでは足りず3次元の図式が必要になるのだがそれは面倒なのでまた今度。
*1:ちなみにここに出てくる五十嵐先生の書かれた文章がネットにアップされており、非常に面白い。こちらに興味もたれた方は是非ご一読を。http://www.parc-jp.org/alter/2008/alter_2008_1_pride.html
「カンニング」と大学
うちの大学は夏休みが7月からなので、一部の学生は現在中間テストがあるらしい。
テストといえば、これはどこの大学でも同じだろうが、ごくまれにカンニングがバレて処分を受ける人間がいる。詳細なペナルティ内容は知らないが、とにかくその一年棒に振るか下手すれば大学からリムーヴされる。
ところで大学のテストにおけるカンニングに関して、たまに極度の潔癖症的な反応を示す人がいる。カンニングに潔癖症も何もあるのかという話だが、下手をすれば「カンニングで取った単位より一生懸命勉強して取った単位の方がよいものである」といった感じのセリフを吐きかねないほどの人がいるのだ。
まさかそんなことはなかろう。カンニングで取ろうが勉強して取ろうが単位は単位である。大学において、単位など卒業条件を満たす/資格の取得要件を満たすための事務的なものでしかない。真面目に授業に毎回出席し、頑張って勉強して手にした単位も、代返を使いながら一夜漬けでどうにか手に入れた単位も、カンニングで手に入れた単位もそれが必要になる現場においては同じ単位でしかない。
むしろ同じになってしまうからこそ、大学側は取り締まる必要がある(と考えている)。勉強して取った単位ならA,カンニングして取った単位ならB、などと序列化できればそもそもカンニングが取り締まられることなどない(そもそもカンニングという概念が失効する)。
そうしたつまらない取締りを吹っ飛ばして、本当に「学ぶ」という行為と「単位の取得」という行為を接続したければ、ペーパーのテストではなく論文と口頭試問で個々に判断するしかない。しかしもちろん規模の大きな学部ではそんなことは不可能である。なので個人的には学部の卒業に単位など要らない、四年間いればそれでいいのではないか、とすら思ってしまう。Aの並んだ成績表を見て誰が彼を優秀だと判断するのか? 機械はそう判断するだろう。だがそれだけだ。大学の事務はそう判断するかもしれない。だがそれだけだ。本当に「学ぶ」という行為がしたければ大学院に行けば良いのでは、と思う。
公共圏か動物か―思想地図における白田―東の議論を巡って

- 作者: 東浩紀,北田暁大
- 出版社/メーカー: 日本放送出版協会
- 発売日: 2008/04
- メディア: 単行本
- 購入: 27人 クリック: 1,022回
- この商品を含むブログ (163件) を見る
思想地図を読み進めている。東浩紀、北田暁大、萱野稔人の鼎談と白田秀彰による論文を読んだのだが、白田と、彼に執筆を依頼した東との間で見識の一致している面もあり、また一見逆に思われる点もあったりしたので非常に面白かった。
簡単に彼らの議論をまとめると、私的領域という歯車と公的領域という歯車があったとき、それらを回すには間に何かのギアがあった方がいいと言うのが白田で、ギアを噛ませず二つがバラバラに、暴走しない程度にうまいこと回り続けるシステムをつくろうよ、というのが東である。以下、両者のそうした違いについて細かく見ていく。
両者の共通点と相違点―断念された主体と公共性
白田は論文「共和制は可能か」の中で、現在の日本を古典的寡頭共和制であるとし、近代的民主共和制への移行可能性を論じている。日本は国家の運営を担う層とその支配に預かる層の間に断絶があり、これが果たして国民が自覚的に支配機構へコミットする体制へと移れるのか、という問題意識である。
結論から言うと白田はそのようなことは不可能だとしている。彼は民主共和制への条件を二つ提示している。一つは支配機構に関わる公的領域(res publica)が、守護・維持に値するということを事実として国民が受けとめていること、そして第二にそのためには公的領域に対して貢献するのだという信念が存在すること。日本においては、少なくとも日本という国家体制に対しては国民はそのような「物語」を事実としては到底受け止めていないだろうとして、白田は日本の民主共和制への移行を否定している。
自らを「主体」として自覚し、積極的にこの国の公的領域にコミットしていこうという姿勢が日本国民にはもはや無い、という認識に関しては白田と東も一致している。社会を所与の「自然」として捉え、そこへの積極的なコミットを拒否するのはまさに「動物」的ではある。しかしその後の方向性については両者は大きく異なっている。東は岩井克人の国家観を参照し、国を会社としたときにlこれまではその保有者を従業員として見てきたが、これからは会社の持ち主は株主だ、という方向に切り替えていく必要があるとしている。従業員はその会社に所属していることを自覚し、積極的に会社の運営にコミットする必要があるが、株主はそうではない。所属を自覚することも、仲間と協調して公共的な側面にコミットする必要も無い。国家に話を戻せば、ナショナリズムだ討議的公共性だというめんどくさい話は抜きにして、とりあえず損得勘定に基づいたドライな関係で国のあり方にコミットしとけば良いじゃないか、というのが東の見識である。
一方白田はそれとはまた異なる形で公共性の確立を目指す。国家という公的領域へのコミットは皆興味が無いかもしれないが、そこに国家ではない、別のものを代入すれば公的領域の復活は果たせるのではないかとしている。
「……我々現在の日本人が近代国家制度としての日本国に対して、もはや積極的に関与できないとしても、現在の我々の生活の安寧と幸福の源泉に対してならば、我々は積極的に貢献しうるのではないだろうか。」*1
巨大化、複雑化したが故に自分の私的な利益との関係性が不透明になった個人―国家間では、その運営に携わるべく積極的に公的領域にコミットするのは難しい。そうではなく、個人と公的領域の関係性が見通せる規模で公的領域を立ち上げれば、私的利益は公的領域の維持によって担保されているという認識を持つことができるのではないか、ということである。そもそも個人が「主体」として公的領域にコミットすることを断念している東と、規模や環境の調節によってコミット可能な公共性を立ち上げようという白田の間には、大きな差が見られる。ローティアンを標榜する東は、公的問題と私的問題を分けることを求め、個人が私的な欲望と公的領域を接続させることを警戒し、北田・萱野との鼎談の中でこう述べている。
「私的な欲望は自由で、公的な議論はとりあえずそれとは関係ないという区別が、この国ではまだ出来ていない。僕はこれを分けるべきだと思う。それに対して一君万民的な『草の根ナショナリズム』を警戒してしまうのは、それが、ひとりひとりの私的な欲望を変えることによって、つまり公共性を私的に欲する人間を増やすことで公共圏を立ち上げようというプロジェクトに見えるからです」*2
もちろん白田は国家に変わる新しい公共圏の立ち上げに、ナショナリズムを持ち出そうとはしていない。だが、それは表層的な手段において明確な差異が見られない、というだけであり根本的な発想においてはこのような差が見られる。
議論の収束点―静的から動的へ
ただし東の議論を細かく見ていくと、この差異は解消不可能な深い断絶というわけでもないように見える。東が警戒するのは、私的な欲望と公的領域を一足飛びに直結させることだ。そうした接続をしている人々の例として彼は「ぷちナショ」や「赤木智弘」を挙げる。彼らは東からすれば私的な問題をそのまま直接公的領域に持ち込んでいる。
そして白田も恐らくそうした人々を肯定することは無いだろう。白田の議論は、個人が所属する私的領域という歯車と社会のコントロールに関わる公的領域という歯車を結ぶ「ギア」を、何に見出すのかという点にかかっている。国家はもはやギアにはなりえない。何か別のものをギアに入れる必要がある。本論文においてはインターネットにその可能性を見出している。そして彼はギアを使わずに私的領域と公的領域を直に接着させることは、想定していないはずである。二つが接触せず、分断した状態を彼は寡頭制共和制としており、民主的共和制からは程遠い、としている。白田の選択肢は、ギアの無い、私的領域という歯車と公的領域という歯車が別々に回転する状態か、ギアによって二つの歯車がかみ合い回転する状態か、その二つである。
東から見れば、そうした白田の考えはぷちナショ的に私的領域と公的領域をショートサーキットさせる者への想定が足りない、ナイーヴなものに見えるかもしれない。また白田から見れば東の動物化に対する消極的肯定は、ギアも無くまた歯車をショートサーキットさせることもなく両方が上手く回り続け、かつ両方とも暴走しないようなシステムを用意しろということになり、それはそれで虫が良すぎる、現実味に欠ける議論になるだろう。
東も指摘しているが、私的領域と公的領域がかみ合うことなくバラバラに、かつ上手い具合に回転してきたのは実はこれまでの日本であり、白田もそれを寡頭共和制と呼び現在の日本の状況であるとしている。だとすれば、何も時間と金を費やしてこのような議論をする必要は無く、二人とも現状万歳の全肯定でいけばいいのだが、そうもいかないらしい。東も白田も、この国の現状や今後に何らかの問題があり、変える必要があると考えているのだろう。おそらく、現状を支えるシステムがもうもたない、というのが彼らだけでなく多くの人々が共有するイメージなのだろう。
個人的な感想としては、現状に対する認識は静的なものであり、今後の社会をどうするか、何をどう動かせばいいのかと言う話は動的なものである。それらの議論を接着させるには慎重というか厳密な議論の摺り寄せが必要であり、ここに挙げられているような議論だけではもちろん不十分だろう、としか言いようが無い。ただ以前のエントリでも書いたが、必ずしも皆が皆動物になれるわけではないなく、東はそうした人々が私的領域と公的領域をショートサーキットさせる危険性を指摘しているが、そもそもそういう発想にすらならず、私的領域を自ら捨てる、壊す者の存在も指摘しておかねばならない。それは歯車がショートサーキットするのではなく、歯車自体が自壊する可能性を含んでいる、ということだ。もちろん白田のように何らかのギアを用意したところでそうした人間が現れる可能性はあるものの、どちらかといえばギアを用意したほうが上手くいけばそうした自壊可能性は下がる気がする。白田は私的領域の離脱/破壊者をもしかしたら救える射程を持つのに対し、東の理論はそうした射程をそもそももたないからだ。*3
「春の文学フリマ2008」に参加します
「春の文学フリマ2008」開催決定!
開催日時 2008年5月11日(日)
開場 11:00〜終了16:00
場所 東京都中小企業振興公社 秋葉原庁舎 第1・第2展示室
(JR線・東京メトロ日比谷線 秋葉原駅徒歩1分、都営地下鉄新宿線 岩本町駅徒歩5分)
※入場無料、カタログ無料配布、立ち読みコーナーあり
logical cypher spaceのシノハラユウキが主宰する批評系サークル「筑波批評社」に加えてもらっています。今回の文学フリマでは、批評系同人誌「筑波批評2008春号」を販売します。
ブース番号:B-56(会場地図)
サークル名:筑波批評社(公式サイト)
GW中、しばらく我が家にプリンタとPCを集めてみんなでシコシコ編集作業をしていました。僕は大体寝オチしてましたが。
その甲斐あって先日ほぼ編集作業を終えることが出来ました。
これがその目次になります
特集はR・ローティ「偶然性・アイロニー・連帯」を読んでの座談会です。計六時間、単純に文字起こしして6万時にも及ぶ大長編をどうにかこうにか同人誌の体に収まるくらいに仕上げてあります。ローティの思想を改めて問う形になっており、非常に中身が濃いものとなっております。是非ご一読を!
ちなみに僕個人は「アイロニカルな共同体―その成立条件」という論評を書かせてもらいました。ローティ的なアイロニーの行く末に果たしてどのような社会が待っているのか、という射程を示そうと意図です。もちろんそこまで大きなことは言えないのですが……。
他にも文学評論からマッチョ・ウィンプ論まで幅広くかつ深い評論が盛りだくさんです。かなりボリュームのあるものとなっているので、是非皆様足を運んでいただければと思います。
「戦後」の<歴史>化
先日ゼミで先生に言われて気づいたのだが、そういえば「戦後」という言葉を最近とんと見なくなった。中曽根首相が「戦後政治の総決算」という言葉を使って以降も、メディアでは自分たちの現在生きている時間を指して「戦後」と呼ぶことはあった気がする。
メタヒストリーという立場に立つと、これは「戦後」なる時間が過去のものになったということを意味する。ではいつから「戦後」ではなくなったのか?「戦後」を字義通りに捉えるなら、戦争の終わった後の平和な状態である、ということになり、そのフレームが消えたということはつまり今は戦時中なのだ、ということになる。安易に接続するならば、それは9.11以降ということになるのだが、この解釈は個人的にはしっくり来ない。
「戦後」なる時間の流れをconstativeに捉えるのではなく、perfomativeに見たとき、我々が自分たちの生きる時間を「戦後」と呼びうるフレームというか条件、メンタリティのようなものが変わったのだろう。それは戦時中だとかそういうことではなく、もう少し大きな枠で見たフレームの変化だろう。
個人的には9.11といったような特定のトピックによって戦後が<歴史>となったというわけではない気がする。我々があの時代を<歴史>とみなすことは、単に今の時代の以前に存在した時間であるということだけでなく、何らかの形で語られたものになる―それが<>が付くということ―ということが必要になる。事実の時系列にそった羅列だけではなく、それがどういったものであったのか、現在から見てどのようなものだったのかということを語られ、かつそうした認識が社会全体で共有されることが必要なのだ。
小泉首相以降、政治は戦後的なるものからの脱却を図ろうとしてきた。戦後政治的なスキームで動いてきた社会の構造は、ベタに信じられる「事実」ではなく、<>付きのもの、他に選択肢があったかもしれないナラティブなものであったのだ、という認識が広まった気がする。彼の靖国参拝への姿勢は、それまでの首相が取ってきた姿勢を<歴史>の中へと押しやり、語られる対象とした。「構造改革」のフレーズは、それまでの政治が「改革」されるべきものであり、我々にそれが何であったのかを語らせた。このように戦後的な時間に<>を付け、語るべき対象とする動きがいくつかの場面で同時多発的に起きたような気がする。9.11もその一つであろうが、それが全てではない。グラデーションを描くように、だんだんと我々の生きる時間から戦後的なものが消え、ナラティブなものとなっていった。
ただし<歴史>がナラティブなものであり、社会との間で往復的な再記述を経て形成されるものだ、という認識が人々の間で共有されているかは怪しい。我々は確かに戦後的な時間を<歴史>の中に追いやり、語るべき対象としてきたが、そうした変化に自覚的でありながら意識的にやっているのかというとそうでもないようだ。戦後・戦中の歴史について、未だ「事実性」の奪い合いは起きている。それが歴史の物語性をより確かなものとしているのだが、彼らはどうもベタに事実性を求めているように思われる。
もちろん<歴史>は我々が単に記述するものであるだけでなく、<歴史>もまた我々を記述する。我々が記述した<歴史>は、その記述を通して我々を規定する。我々が何を<歴史>としたのかを見ることによって、我々の現在の社会的なメンタリティを知ることが出来る。
ただ「戦後」なるものが<歴史>の一部となったことはあるにしても、果たしてそれがどのような<歴史>であったのかということについては未だ共有されているものが少ない気がする。ポストモダン的に言えばそれは共有されないまま終わってしまうのかもしれないが。
個人的な興味としては、<歴史>が物語であること、そのナラティブさを共有している人たちと、単なる「事実性」にのみ拠ってベタな見方をする人たちとの間で大きな乖離が起きているように見える。その乖離が現在の社会でいくつかの「問題」として表面化しているように思う。
